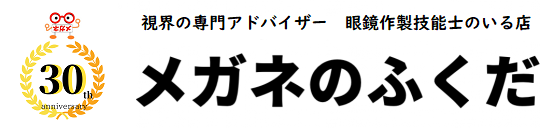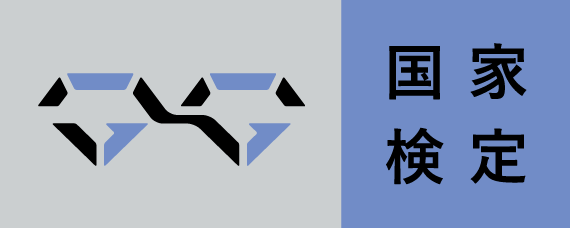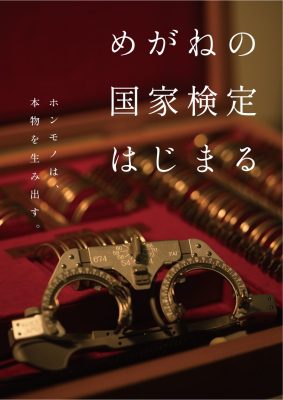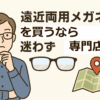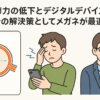眼鏡作製技能士とは
眼鏡作りに関する初の国家検定資格
国家認定資格である眼鏡作製技能士(がんきょうさくせいぎのうし)について
技能検定制度の一種で、令和四年度から新設されました。
公益社団法人日本眼鏡技術者協会が実施する、
眼鏡作製に関する学科及び実技試験に合格した者をいいます。
眼鏡作製技能士(1・2級)の制度があり、メガネのふくだ店長は1級資格者であるとともに、
プライム会員(眼鏡作製技能士の中でも、知識・スキルの向上を図る一定期間のリカレント教育を修了した者)でもあります。

(関連サイト→厚生労働省のHP 技能検定「眼鏡作製職種」を新設)
眼鏡作製技能士の1級と2級の違いについて
1級【後進の目標となる眼鏡作製技能士】
- 眼鏡市場のトレンドを把握し、顧客の眼鏡に関する潜在的なニーズをくみ取り、最新の技術で製造されたレンズ、フレームを活用し、顧客に最適な眼鏡の提案ができる。
- 眼鏡作製に必要な詳細な知識・技能を身につけているのみならず、それらを体系的に理解しており、他の眼鏡作製従事者の指導や育成を実施することが可能である。
- 眼鏡作製知識・技術だけでなく、コンプライアンス、眼科専門医との連携に関する十分な知識を持ち、総合的なマネージメント能力を持つ。
2級【業界のベースとなる眼鏡作製技能士】
- 顧客の眼鏡に関するニーズをくみ取り、販売されているレンズ、フレームを活用し、適切な眼鏡の提案ができる。
- 眼鏡作製に必要な概略の知識・技能を身につけており、顧客のニーズに応じた眼鏡を作製する事が出来る。
認定眼鏡士との違いについて
端的に言うと、
認定眼鏡士(令和4年3月まで実施)は、公益法人の任意の資格だったのに対して、
眼鏡作製技能士は、国家検定資格であること。です。
認定眼鏡士は優れた制度であるにもかかわらず、一般消費者に対する知名度が低く、
残念ながらメガネ販売者の基準とまではならなかった…というのが個人的な感想です。
これからは、きちんとした眼鏡店で働くには眼鏡作製技能士資格の取得が、
事実上必須とされる時代になると思いますし、
そうなる事でメガネユーザーの皆様が間違った選択をして困るケースが少なくなることを期待しています。